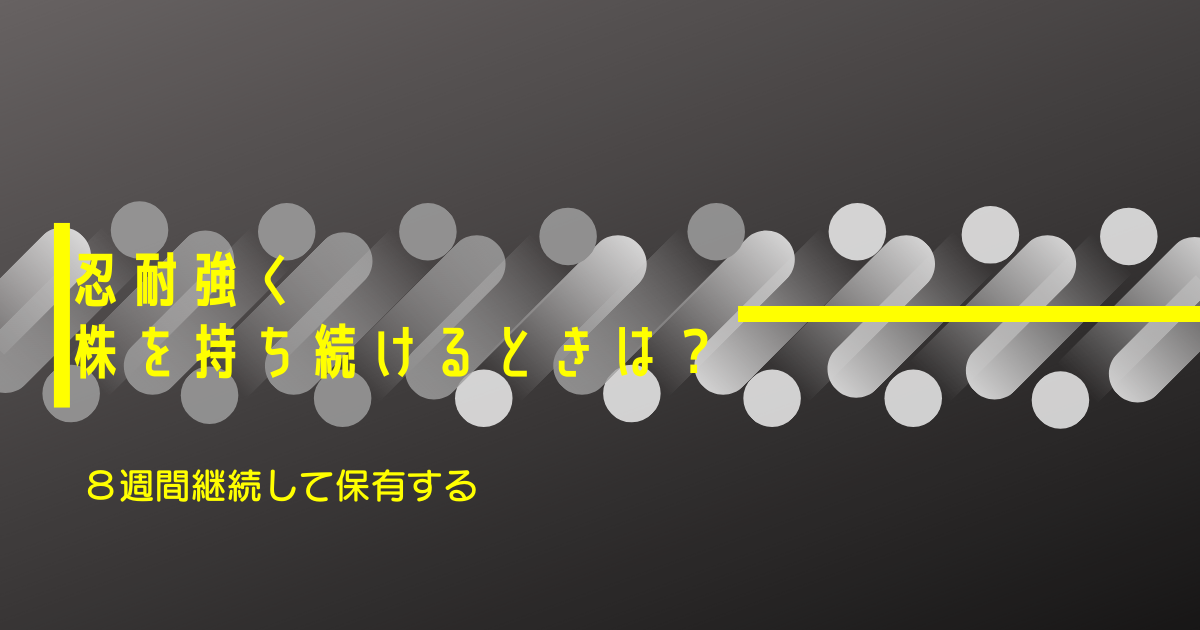
裏打ちされた売りのサインには、どのようなものがあるかを知ることが大事です
本書の中でも特に重要であり、入り口を教える投資本が多い中で、出口を示す本書は貴重です。
最後は、どんなときに我慢して株を持ち続けなればならないか学びましょう。
- 忍耐強く株を持ち続けるとき
- 目標株価まで保有する
- マーケット全体の動きを分析する
- 損切りラインまで持ち続ける
- 幻の含み益にしてはいけない
- 8週間以内に大化けしたら8週間は持ち続ける
- ファンダメンタルを入念に調べて自信を持つ
- 忍耐こそが金を生む
- まとめ
- おわりに
- 免責事項
忍耐強く株を持ち続けるとき
- いつ売るかという判断に密接に関係するのは、いつまで持ち続けるか、ということだ。
いつ売るかという判断は、いつまで持ち続けるかと表裏一体です。
今回は、そんな時に役にたつオニールの助言を紹介したいと思います。
目標株価まで保有する
- 今後1〜2年の収益予想から、ベースをブレイクアウトしたあとに株価はどれだけ上昇しそうか、そしてPER(株価収益率)はどれだけ上昇しそうか、という見通しが立てられるような成長株を買う。
- 最高の収益増加を見せる大化け銘柄を、これという正しいタイミングで買い、そしてその判断が正しかったか間違っていたかが実証されるまで、忍耐強く持ち続けることがあなたの仕事なのである。
今後の収益予想から理論株価を算定する方法が、最初に考えられます。
そのうち本書で紹介している、PERを使った詳細な予測手法は以下の通りです
- 例えば、今後2年間の収益の見通しの数値を、その銘柄のチャートで見付けた最初の買いポイント時点のPERの数値で掛け、そこで得た結果に100%か100%強を掛ける。
- この計算は、成長株が大きく値を上げたときに、平均的にPERがどの程度上昇する可能性があるかを測定するもの。
具体的な計算を示すとイメージがつくかと思います。(pp.214)
たとえば、最初の買いポイントにおけるPERが40倍、株価43.75ドルとします。
このときに、40に130%をかけて得た数値(=52)が今後の伸び幅となり、この銘柄はPER92(=40+52)倍にまで伸びる可能性があると仮定します。
その次に、2年後の予想EPS1.45ドルにこの予想PER92倍を掛けます。
この結果出た数字133.4(=1.45×92)ドルが、予想株価と計算できました。
成長株を売る目安が欲しいという人には便利でしょう。
同じく成長株投資で有名なミネルヴィニも同様の方法を採用しています。
マーケット全体の動きを分析する
市場全体が弱いと、個別株も引きずられて上がりづらいです。
本書では『インベスターズ・ビジネス・デイリー』の「ザ・ビッグ・ピクチャー」を紹介しています。(有料です、日経新聞みたいなものでしょうか?)
https://www.investors.com/category/market-trend/the-big-picture/
マーケット全体が売り抜けや天井を示したり、既に弱気相場入りしていると、新規に株を購入しても失敗に終わることが多いため、傍観するのがよいでしょう。
マーケットに逆らってはいけません。
損切りラインまで持ち続ける
通常の調整で大化け銘柄を逃すのはもったいない。
新しい強気相場が始まって1~2年の間はある程度の余裕を与えて、株価が損切りラインを切るまで持ち続けましょう。
もちろん買値の8%損切りは絶対です。
証券アプリのアラートをつけるなりして注意しましょう。
損切りラインを下回っても、復活することはよくあります。
しかし、そんな気まぐれでトレードしていては自信がつくはずもありません。
何より百回に一度の大暴落となった場合は、マーケットから(メンタル的にも)退場することになってしまいます。
まずは決めたルールに淡々と従うことが重要です。
幻の含み益にしてはいけない
- 20%近く上昇したような株は、絶対に損失に転じるまで持ち続けてはならない。
20%近く上昇したような株は、絶対に損失に転じるまで眺めてはいけません。
下落するのを眺めてしまう心理として、過去の高値を意識してしまい、ここで売るのは悔しくてやりきれないと思ってしまうからです。
七面鳥の話でも出てきましたね。
繰り返しになりますが、眺めているその時点で利益確定をし損ねたという過ちを犯しています。
それをマイナスに転じるまで我慢するという二重の過ちを犯してはいけません。
すべての損失をできるだけ最小限に抑えることが私たちのやるべきことの一つです。
8週間以内に大化けしたら8週間は持ち続ける
大化け銘柄が最高に熟すまでには、それなりの時間がかかります。
8週間以内に20%を超える銘柄は、以下の理由がない限り8週間保有し続けるべきです。
わずか1~3週間で20%上昇する銘柄は、テンバガーの可能性があります。
1〜3週間で化けた銘柄を8週間保有した方が、当然ながら失敗する可能性は低くなります。
大化け銘柄は少し甘めに見る
大化け銘柄は急上昇する分だけ、その反動で大きく調整することは少なくありません。
期待値の観点から、大幅なリターンが見込めるなら、リスクもそれなりに背負う価値はあります。
もちろん大化けしたら甘く見るのであって、大化けする見込みがあるからといって、最初の損切りのルールを破ってはいけません。
なお10週移動平均線への押しについては、第1章のチャート週を見ると増し玉しているケースを数多く見つけることができます。
ファンダメンタルを入念に調べて自信を持つ
- 新しい強気相場が始まって最初の2年間が、最も利益が大きく、リスクが少ない期間になるものだが、それには勇気、忍耐、そして利益を見つめる目が必要だ。
- 企業やその製品について熟知し深い理解を持っていれば、何度かはやって来る通常の調整をじっと待ってやり過ごすだけの強い勇気が持てるだろう。
テクニカル要素ばかりでなく、その土台たるファンダメンタルを一通り調べておけば、いざ我慢の時が来た時にも自信を持って株を持ち続けることができるでしょう。
オニールはけっしてチャートだけを使うのではなく、ファンダメンタルをCAN-SLIMという形で重要視しています。
ただしあまりに入念に一つの企業を調べると、愛着が湧いてしまい短所を甘く見てしまうこともあるので、公平に結果を受け入れる精神が重要になります。
忍耐こそが金を生む
- 投資の目的は正しい判断を下すことだけではなく、正しい判断を下して大きく儲けることである。
- 「思考が大金を生むことはない。忍耐こそが大金を生むのだ」とリバモアも言っている。
- 正確な判断力と忍耐力を同時に持ち合わせている投資家は少ない。
- 株が大きな利益を生むには、それなりの時間がかかるのだ。
口だけで行動が伴わない人は、探せばいくらでもいます。
オニールが言いたいのは、思うだけでは足りず、実際に行動ができて初めて儲けることができるという、至極当たり前なことを述べています。
しかし実際に我慢し続けるというのは、簡単ではありません。
せっかくの含み益が減ってしまうという不安や恐怖と戦うのは、かなり苦労します。
これまで紹介したルールに基づいて、我慢できずに小さく利確してその後の上昇を逃したりするのを防ぐことが、大化け銘柄を本当に手に入れる第一歩となるでしょう。
まとめ
- いつどのように売るかという判断は、いつまで持ち続けるかと表裏一体
- PERから算出した目標株価まで保有する
- マーケットが弱気相場に入ったら、持ち株の大半を売却するとよい
- ブレイクアウト後による調整が起きても、損切りラインまで我慢して持ち続ける
- しかし大きく上昇して得た含み益が、すべて泡となるまで我慢するのはやめよう
- 購入後8週間以内に大化けしたら、8週間は持ち続けよう
- 大化け銘柄となった株は、10〜15%の通常の調整から振り落とされないように、手放すにはある程度余裕を持たせるとよい
- ファンダメンタルがしっかりしていれば、それだけ大化けする確率は上がる
- 実際に行動して我慢できたからこそ、大化け銘柄の恩恵を受ける
おわりに
市場で勝者になるには、まず良い売り手と良い買い手になることから始まります。
ここまで読み終えた私たちは、買う技術と売る技術を学びました。
本書の中でも特に重要な部分ですので、何度も読み直しましょう。
しかし、これだけではまだ足りません。
しっかりした資金計画がなければ、凄腕トレーダーも破産してしまいます。
勝てるようになり、調子に乗って取引単位を増やし破産しては意味がありません。
そこで次回は資金管理について読んでいきましょう。
ポートフォリオの扱い方や取引単位の決め方など、やらなければならないことはまだたくさんあります。
gyatuby.hatenablog.com
免責事項
- 当ブログで紹介している方法や技術、指標が利益を生む、あるいは損失につながることはないと仮定してはいけません。
- 過去の結果は必ずしも将来の結果を示すものではありません。
- 紹介する実例は、教育的な目的でのみ用いられるものであり、当ブログに書かれた手法・戦略による売買を勧めるものではありません。
